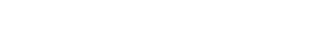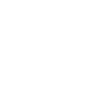社会啓発・連携
防衛・核燃マネーが公共サービスの財源に
「人口減少社会に未来を学ぶ」。こうした気づきを得た理由の一つに、コロナ前まで数年間、青森県下北半島の中山間地域にある歯科医院へ仕事で定期的に訪れ、消滅の危機さえ指摘される人口減少地域の動向を間近で観察する機会があったことが挙げられます。
平日朝7時台の羽田発三沢行きの機内は、ダークスーツ姿のビジネスマンとカジュアルな服装の外国人で占められています。空港に到着すると、まず目に飛び込んでくるのは日本原燃株式会社の電飾看板。続いて、ロビーで出迎えるのは迷彩服に身を包んだ在日米軍兵士という、異様な光景です。このため、勘の鈍い人でも、到着から15分も経たないうちにこの地域の特異性に気づくことでしょう。
この地域の自治体には「防衛マネー」と「核燃マネー」が流れ込み、人口減少地域の生活と産業を支える重要な財源となっています。調べてみると、ある村では、人口の3分の1が核関連産業に従事しており、放射性廃棄物処理に関わる労働力となっていることが分かりました。
こうした自治体に交付される防衛・核関連の補助金は、「小中学生の医療費自己負担分を助成し、子育て世帯の負担を軽減することで、子どもの保健および生活環境の向上を図る」といった子ども医療費助成事業などに充てられ、条例化されることで地域住民に還元されていきます。
このように交付された防衛・核燃マネーは、医療・介護・道路・公民館などの住民生活の利便性向上や産業振興に寄与する事業の主な財源となっています。米軍基地や原発を受け入れることで生じるリスクを、自治体の公共サービス財源として転換することで、大多数の国民はより安心で快適な生活を享受し、それに関わる企業は利潤を得るという構図が浮かび上がってきます。
一方で、米軍基地や原発を受け入れた地域では、公共サービス財源確保のためのリスクアセスメントが課題となり、官対民、公対私といった対立が生じていることもマスメディアを通じて広く知られています。さらに、原発は、いざという時には核兵器へと転用可能な側面も持ち合わせており、こうした「ダークサイド」を生み出している現実にも目を向ける必要があります。
官民連携の新たなプラットフォーム
先般、同行した富士通Japan社(以下、富士通J)が主導する北海道神恵内村予防歯科プロジェクト(以下、予防歯科PJ)では、官対民、公対私といった二項対立や、いわゆる「ダークサイド」の側面を感じることはありませんでした。
それは、この自治体が人口約800人の漁業を主産業とする村であり、積丹半島の日本海側斜面に張りつくように存在しているからかもしれません。そこに暮らす人々は、生きること、生活することに必死であり、「村が消滅するかもしれない」「村民全員が生き残ることに必死だ」という切実な思いが、ひしひしと伝わってきました。
行政と村民が対立している、あるいは関与する民間企業と行政が対立しているといった、従来の図式でこの地域を捉えることはできません。それこそが、人口減少と高齢化が極限まで進んだ地域の実態なのかもしれません。
神恵内村では、課題が複雑化・深刻化するなか、行政だけでは解決できない困難な壁が立ちはだかっています。その壁を乗り越えるためには、地域住民、行政、民間企業、NPOなどの活動団体、専門家といった関係機関や関係者が、それぞれの強みを活かし、連携して解決に取り組む必要があります。本来であれば、行政(公)が担うべき仕事を、民間企業(私)が連携・協働して推進しようとしていること。そして、行政(公)との連携・協働が、民間企業の利潤動機とうまく調和することは、言うまでもありません。
神恵内村での予防歯科PJは、民間企業(私)である富士通Jが主体となり、専門集団である一般社団法人日本オーラルフィジシャンフォーラム(以下、JOF)がそれを支えています。富士通Jはすでに、神恵内村の養殖産業の管理システム構築や、ITを活用した小中一貫キャリア教育の展開を進めており、民間企業としての利潤も確保しつつあります。さらに、予防歯科PJが進展していくことで、産業振興、教育、医療といった従来は自治体が担ってきたサービスの多くに富士通Jが関与することになり、神恵内村は新たなプラットフォームへと生まれ変わっていくでしょう。
多くの民間企業は、顧客の減少を新たなプラットフォームの構築によって補い、一方で人口減少地域は、そのプラットフォームづくりに関わる「関係人口」の増加が見込めるという win-win の関係が成立します。神恵内村では、公と私が一体となって 地域課題を解決し、ニーズを満たす動きが当たり前になっていくことで、将来的には域内の資金循環が再構築される という、大きな変化が起こり始めるのではないかと思います。
神恵内村の根幹にある原理が変わると、自治体の枠組みも変わっていくでしょう。従来の自治体は、税を通じて資金を集め、医療、子育て、上下水道、ゴミ収集などのサービスを提供する役割を担っていました。しかし、神恵内村では、公と私が連携・協働しながら、産業振興、教育、健康医療などの各分野におけるキーマンをつなぐことが、自治体の新たな役割として求められる ようになっていくはずです。
「新潟コシヒカリ」のような予防歯科を
公 の神恵内村と 私 の富士通Jは、それぞれが抱える課題や連携における利害が一致し、その一環として予防歯科PJが存在しています。共 のJOFが専門家集団としてこのプロジェクトに参画するためには、JOF自身の目的、利益、そして支援できることを明確に表明する必要があります。その上で、世帯収入が300万円に満たない地域において、JOFが提唱する予防歯科を地域住民に受け入れてもらうためには何が必要かを考えることが重要です。
少なくとも、現行の医療保険制度に欠陥があるからといって、社会保障としての医療保険そのものを否定してしまっては、この予防歯科PJは成立しません。JOFの予防歯科をどのように活かしていくのか。そのためには、自治体への予防メンテナンス補助金制度の説明、そして何よりも神恵内村の歯科医師や医療関係者が予防歯科PJを担っていくための意識醸成と育成支援が必要となるでしょう。
JOFの役割を上述のように考えると、その目的と利益は、新たな「予防歯科ビルダー」としてのポジションを社会に表明することにあるのではないかと思います。そのためには、医療が行政のあり方に左右されることは、現状では私たちの手に余る問題であると割り切り、だからこそ 予防歯科医療の専門家グループとしての社会的役割を模索し、積極的に担っていくべき です。神恵内村での予防歯科PJは、行政的な障壁が少なく、自治体や地域の歯科医師に対して適切な助言や提言を行い、医療として最適な予防歯科のあり方を示すことができる好機と捉えることができます。
少し話がそれますが、日本の現行法の多くは、第二次世界大戦後に制定されたものです。食糧管理法(食管法)と健康保険法は、いずれも全体主義的な性格を持つ1940年代、敗戦前の社会で制定され、その枠組みのまま今日まで存続しています。しかし、食管法はコメ不足の解消とともに形骸化し、「政府米」と「自由米(ヤミ米)」の間に、「新潟コシヒカリ」に代表される 「自主流通米」=「うまいコメ」 が誕生し、マーケットも変化していきました。その後、食管法は 「売れるコメ作り」 を基本に置いた食糧法へと改正され、現在ではコメの価格や生産、流通に関する政府規制が大幅に緩和され、市場原理が導入されています。
その一方で、健康保険法に関していえば、歯科では 歯科医師の数が不足から過剰へと転じ、75~84歳の 51%が「8020」を達成 したとされる現在でさえ、政府の規制下に置かれています。歯科医師は、共同体的規制ともいえる 医療保険制度に縛られた「ムラ的環境」 の中で、その職業に甘んじざるを得ない状況にあります。そのため、保険医としてグローバルスタンダードとされる歯科医療を目指すには、現行の保険制度の運用だけでは限界がある のが現実です。しかし、だからといって 保険制度を頭から否定してしまっては、無批判に現行制度を受け入れる歯科医師の姿勢と何ら変わらず、歯科医療の未来を拓くことにはつながりません。
予防歯科が一般的になった今こそ、予防歯科PJを皮切りに、JOFは予防歯科分野での「自主流通米」=「うまいコメ」の確立を目指すべきではないでしょうか。 診療報酬改定に左右されず、経済格差にも動じず、そして 北欧・北米の歯科医療にも伍していける 「自主流通米」のような予防歯科の確立こそが、企業との連携の意義であり、社会が求める公益性の高い歯科医療の形 ではないでしょうか。
「新潟コシヒカリ」のような予防歯科に近づくために、私たちは何をすべきか。 その問いを 当たり前のものとして持ち続けることこそが重要 なのではないでしょうか。
過去の社会連携・啓発
- セミナー2024年12月12日
「第12回日本介護予防・健康づくり学会大会フォトレポート」を掲載しました - ニュース2023年12月5日
神恵内村歯科診療所が予防型歯科医院としてスタートしました - ニュース2022年9月13日
【企業連携レポート】ローカルに学ぶ 〜人口減少社会の未来と予防歯科のカタチ〜 - セミナー2022年6月27日
「富士通全社健康経営推進施策・予防歯科セミナー開催レポート」を公開しました