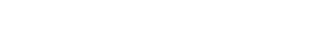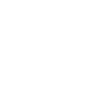開催概要
口腔マイクロバイオームがもたらす口腔と全身の疾患と健康」
・JOF会員は敬称を省略しております
フォトレポート
◉口腔マイクロバイオームと全身疾患のつながり
東北大学大学院歯学研究科・特任教授 髙橋信博先生
■ “病気の原因”を超えて、微生物の視点で世界を見る
JOFセミナー第2回の講演では、東北大学名誉教授・特任教授であり、同大学総長特別補佐(グローバル戦略室)も務める髙橋信博先生より、口腔マイクロバイオームの代謝がいかに全身の健康や疾患に影響を与えているかについて、最新の生化学的知見に基づいた大変示唆に富むご講話をいただきました。
口腔マイクロバイオームは、もはや歯周病やう蝕といった口腔内疾患の原因としてだけでは語れません。近年では、腸内に限らず、口腔内の微生物叢(=マイクロバイオーム)が産生する代謝物が、免疫、代謝、炎症といった全身性のプロセスに影響することが明らかになってきました。
髙橋先生は、この複雑な現象を多角的に紐解きながら、「口腔とは何か」「医療とは何を対象にしているのか」を問い直すような、大きなスケールの話を展開されました。
■ 口腔内の“場所”が生む、代謝の違い
講演の冒頭では、「口腔マイクロバイオームは“菌そのもの”ではなく、“菌とその生息環境のセット”で理解すべきである」と強調されました。
たとえば歯肉縁上では、食事に含まれる糖質が主要な栄養源となり、それを代謝する菌によって乳酸や酢酸といった有機酸が産生されます。これが歯の脱灰を引き起こし、う蝕のリスクとなります。
一方で歯肉縁下では、歯肉溝滲出液に含まれるタンパク質やアミノ酸が菌の栄養源となり、代謝の結果としてアンモニア、硫化水素、短鎖脂肪酸などが産生されます。これらの物質は炎症を促進し、歯周組織を破壊する因子となります。
このように、同じ「口腔内」であっても栄養環境と酸素濃度の違いによって微生物叢が変化し、疾患のパターンも変わってくるという点が、非常に明快かつ論理的に示されました。
■ 代謝物が語る“もう一つの健康観”
さらに先生は、口腔内で産生される代謝物(メタボライト)が、局所的な炎症だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす可能性を示す研究について言及されました。
たとえば、短鎖脂肪酸(SCFA)は一部の濃度では免疫調節作用を持つ一方で、過剰になれば炎症促進に転じる可能性があります。硫化水素は細胞毒性を持ち、慢性炎症に関与することが指摘されています。加えて、近年の研究では、これまで知られていなかった食物成分由来の様々な代謝物が見出されています。こうした代謝産物は唾液や血流を介して全身に波及し、糖尿病、心血管疾患、認知機能障害といった疾患との関連、さらには健康との関連が疫学的・機能的に示唆され始めています。
ここでは単に「病原性菌が悪さをする」という一元的なモデルではなく、「微生物とその代謝環境との関係性をどう評価し、どう整えるか」という包括的な健康観が提示されました。
■ “環境が病気をつくる”という視点
講演の中盤では、環境の重要性を示唆する例として、発展途上国のスラム街の話も紹介されました。
そこでは、環境の悪化、すなわち経済的貧困やそれに伴う公衆衛生学的環境の悪化が、そこに住む人々の体と心の健康を脅かしています。こうした衛生環境の悪化は、単に健康リスクだけではなく、子どもたちの成長、教育、社会参加にまで負の影響を与える構造的な問題です。
「歯周病もまた“環境が悪化した結果”として理解することができる」という先生の言葉は、私たちの臨床的視野を一段深いところへ導いてくれました。
医療が“病気を治す”ことにとどまらず、“病気が生まれる環境”をどう捉え、どう介入するかが問われていることを、改めて突きつけられるような瞬間でした。
■ 社会を読む“知の力”としての歯科
印象的であったのは、講演全体が、医学・生化学・環境学・社会学といった複数の学際的知見を有機的に統合しながら展開された「知の構築過程」をなぞるような構成であった点でした。派手な映像や演出を排したシンプルなスライドのみを用いた2時間半にわたる講演でありながら、聴衆の集中が途切れることなく維持されていたのは、提示される情報の深度と、その論理的な構造性によります。
とりわけ注目すべきは、臨床や疫学の知識にとどまらず、社会的文脈を視野に入れながら語られる内容に、現代医療における「実践知」と「理論知」の橋渡しを試みる知的態度が一貫していたことでした。本講演は、歯科医療の枠を超えた“知の体系化“の試みとして位置づけるにふさわしく、まさに「社会を読む力」としての医療者の知性を体現していたと言えるでしょう。
■ おわりに
髙橋先生の講演は、単なる専門知識の伝達ではなく、「私たちは何を診ているのか」「何を診ずに済ませてきたのか」を問い直すきっかけとなるものでした。
歯科医療が今後、う蝕や歯周病といった疾患管理にとどまらず、マイクロバイオームや代謝という切り口から全身の健康と社会環境にまで視野を広げるべきことを強く感じました。
このような思索と臨床と教育が融合する場に立ち会えたことを、深く感謝申し上げます。
JOF事務局
◉「形だけで終わらせない! 初期治療・再評価の視点」
JOF歯科医師・杜塚 美千代
■ 初期治療と再評価の再定義──歯科医師こそ触れるべき“臨床の原点”
2025年7月に開催されたJOF会員向けセミナーでは、杜塚美千代先生より『形だけで終わらせない! 初期治療・再評価の視点』をテーマにご講演をいただきました。
これまで“歯科衛生士の領域”として認識されがちだった初期治療。しかし本講演では、それを「歯科医師の臨床力を鍛える場」として再定義し、チーム医療の真価を問い直す視点が提示されました。以下に、講演の要点をレポートとしてお届けいたします。
■ 任せるには、自らができること
冒頭、先生は熊谷崇先生の言葉を引用されましたー「できるからこそ任せられる」。
TBI、保健指導、初期治療――。一見すると“歯科衛生士に任せることができる業務”と捉えられがちなこれらの領域について、先生は明快な問いを投げかけます。
「本当に“任せて”いるのか? それとも、触れたことがないから“押しつけて”いるのか?」
この問いかけは、特に若手歯科医師や、開業間もない歯科医師にとって大きな意味を持ちます。自らが経験しないまま歯科衛生士に業務を委ねてしまうと、指示は表面的になり、共有は一方向になり、評価も定型的になりがちです。結果として、チーム医療の基盤は脆弱になります。
実際に手を動かし、患者と対話し、改善と後戻りのプロセスに立ち会うこと。それこそが、臨床を言語化し、他職種に伝える土台になります。「できる」からこそ、真に「任せる」ことができる。その原則を、改めて私たちに投げかける出発点となるお話でした。
■ 初期治療には“保健指導”としての側面がある
講演の中心には、初期治療の本質的な捉え直しがありました。「初期治療は、単なる処置の集積ではない。歯周基本治療やう蝕の非修復的アプローチを通じて、患者の生活習慣と向き合い、行動変容を支援する重要なステージである」と先生は語られました。
むし歯や歯周病が生活習慣病である限り、患者自身の行動変容がなければ、真の意味での“治癒”や“再発予防”は成立しません。そのため、処置のみならず、生活背景に目を向け、気づきと習慣形成を支援する臨床的コミュニケーションが欠かせないのです。この文脈においては、TBIや動機づけなども単なる技法ではなく、“患者との共同行為”として再定義されます。講演を通じて筆者が特に印象的に感じたのは、歯科医師が初期治療に関与することで、処置の場が患者にとって「生活改善のスタートライン」となり得るという可能性です。患者との初期的な関わりにこそ、行動変容を促す力が宿るーそのように読み取りました。保健指導的な側面を併せ持つ初期治療。歯科医師がその意味を理解し実践することで、支援のあり方や患者との関係性は大きく変わってくるのではないでしょうか。
■ 数値ではなく、“人”を見る
初期治療やメインテナンスにおいて、PCRやBOPなどの数値は重要な指標です。しかし、杜塚先生はそれらの“限界”と“誤解”にも注意を促されました。たとえば、同じPCR15%という数値であっても、プラークの厚みや付着している部位、炎症の程度によって、臨床的な意味合いは大きく異なります。さらに、患者の炎症反応の出方、ストレス耐性、全身疾患の影響など、いわゆる“口腔の感受性”にも個人差があることを示されました。
「この数値の背景には、どんな生活があるのか?
この口腔は、どういう“反応特性”を持っているのか?」
この問いかけは、定量評価から“観察と理解”へのシフトを促します。数字の背後にある“人間の文脈”をどう読み取るか。それが歯科医師に求められる、臨床家としての洞察力であり、見逃されがちな患者の変化に気づく力であると、そう語られていました。
こうした視点は、初期治療のみならず、後に続く再評価の質や意義にも深く関わってくることが示唆されました。
■ 初期治療は“共有”の時間でもある
「次の一歩を共に考える時間」というイメージは、一般的には“再評価”の場面と重ねられがちですが、杜塚先生の講演では、むしろ初期治療の段階こそが、そのような“共有”の土台となることが強調されました。
行動変容ステージに応じた声かけ、患者が“自分で決めた”と感じられるゴール設定、生活背景への共感、こうした支援の在り方が、初期治療のプロセスにおいて丁寧に実践されることが重要であることも語られていました。このような支援型のコミュニケーションが積み重なることで、初期治療は単なる処置の時間ではなく、信頼関係を築き、今後の治療計画を“患者とともに”考える出発点となります。初期治療での“共有の質”が、その後の診療の在り方にも波及していく、そうした視点を提示する講演でした。
■ 初期治療の経験が“教える力”を育てる
今後、多くの歯科医師がチームを率いる立場に立つことになります。そのとき、単にマネジメントや分業の視点ではなく、「育てる力」や「教える力」が求められます。
初期治療やその中での支援的関わりを自ら経験し、現場での患者の変化や失敗に立ち会ってきた歯科医師こそが、後進に“語れる臨床”を持っています。どんな問いかけが患者の行動を変えたのか、どんな観察が問題の兆候に気づかせたのか、そうした経験は、臨床現場で蓄積された“暗黙知”です。この暗黙知を他職種や若手に伝えること。それが、歯科医療における“継承”の第一歩となります。「任せるために経験し、経験を語ることで任せる力が育つ」。その循環こそが、成熟したチーム医療の実践に必要な視座であると、先生は語っておられました。
■ “見る・触れる・支える”を再び臨床に
杜塚美千代先生のご講演は、若手にとっては「臨床の入口」の再確認となり、経験を積んだ歯科医師にとっては「チームを導く立場としての再定義」となる内容でした。初期治療とそのプロセス、そこにこそ、歯科医師の臨床姿勢が表れます。患者の人生と並走し、言葉にならない変化に気づき、支援するという“臨床の力”をもう一度取り戻すということ。それが医療の出発点であり、原点である。
初期治療は、医療の下支えではありません。そこにこそ、診療の哲学が宿り、チームの礎石があり、未来の歯科医療が始まるという、その本質を、歯科医師一人ひとりが自らの言葉で語れるようにするために、今こそ“臨床の原点”に触れるべき時なのかもしれません。
JOF事務局